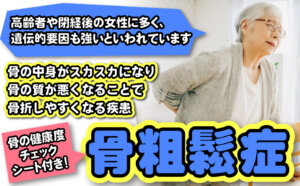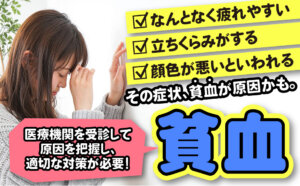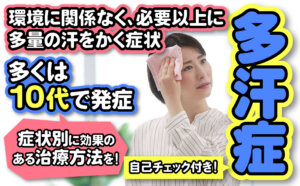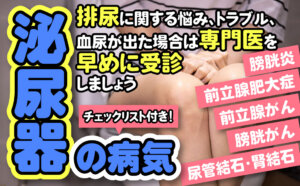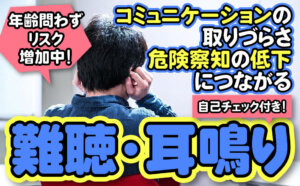マダニから自分・家族の身体を守る!咬まれる前後に知っておきたい正しい知識と対策
夏のおでかけなどで、アウトドアイベントも増えてくるこれからの季節。知らぬ間に忍び寄る影。マダニに注意をしないと、楽しいはずのひとときが思わぬ危険と隣り合わせになるかもしれません。
監修・取材協力:ぎなん皮ふ科クリニック
伊藤 秀明 院長

マダニに注意! -基礎知識
知らぬ間に皮膚に付着している可能性のあるマダニ
マダニは、森林や草むらなどに潜んでおり、人や動物が通りかかった際に体に取り付き、皮膚に口を差し込んで血を吸います。マダニは目視で確認でき、吸血前と吸血後でマダニの大きさが変わるのも特徴です。吸血前の体長は2~3mm程度ですが、吸血後で満腹になると5mm~1cm程度までパンパンに体が膨れ上がり、まるでほくろのような大きさにまでなります。咬まれた箇所の周辺には、赤みや痛みが出ることもあります。

マダニに注意! -皮膚に付着したときの対処法
マダニに皮膚に付着していても、無理やり取らないこと!
マダニは人や動物の皮膚に、口器(こうき)を突き刺して血を吸います。マダニの口器はギザギザの歯を持つ口下片で構成されており、それを皮膚に固定して吸血しているのです。この口器は非常に複雑な構造をしており、一度皮膚に挿入されると、まるで釣り針の「かえし」のようにひっかかり、簡単には抜け落ちないようになっています。無理に引っ張ると口器が皮膚の中に残ってしまう可能性が高く、感染症のリスクが高まる危険性があります。速やかに皮膚科を受診し、適切な方法で除去してもらいましょう。
マダニに注意!-マダニとダニの違いは?
一般的なダニは、主に家の中に生息し(布団やソファ、カーテンなど)、人のフケや垢、食べかすなどをエサとしています。一方、マダニは屋外に生息し(森林や草むら、藪、畑など)、人や動物の血を吸って生きています。
マダニに注意! -マダニに咬まれることで心配される感染症
マダニに咬まれると、さまざまな感染症を引き起こす場合があります。主に、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」「ライム病」「日本紅斑熱」などが挙げられます。
「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」は、38℃の発熱や食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢、倦怠感、リンパ節の腫れなどの症状があらわれます。治療は、症状を緩和するための対症療法が中心になります。抗ウイルス薬として「ファビピラビル」が承認されています。
「ライム病」は、咬まれた部位に赤い皮疹(遊走性紅斑)が出現します。倦怠感や発熱、筋肉痛、関節痛などを伴うこともありますが、症状が軽いと気付かない場合もあります。治療は、テトラサイクリン系薬が有効です。

マダニ からの感染症に注意 高熱、発疹、倦怠感などがみられる場合、SFTSや日本紅斑熱にかかっているかも。これらを総称して「ダニ媒介感染症」と言います。 暑さがゆるみ、野外活動が増える季節になってきました。まだまだ熱中症に気をつけると同時に草むらでの マダニ の吸血に気をつけましょう。
マダニに注意! -野外活動を安全に楽しめるために気を付けること
野山や草むらでの活動が多い時期ですが、同時にマダニの活動も活発になっています。マダニは時に重篤な感染症を媒介するため、適切な対策が必要です。
□ 長袖・長ズボンを着用、首にタオルを巻く
□ 足首が隠れる靴もしくは、長い靴下を着用
□ ペットなどに付着していないか確認する
□ 虫よけスプレーを使用する
□ 森林や草むらなどに不必要に立ち入らない

●マガジンタイプで読みたい方はこちら