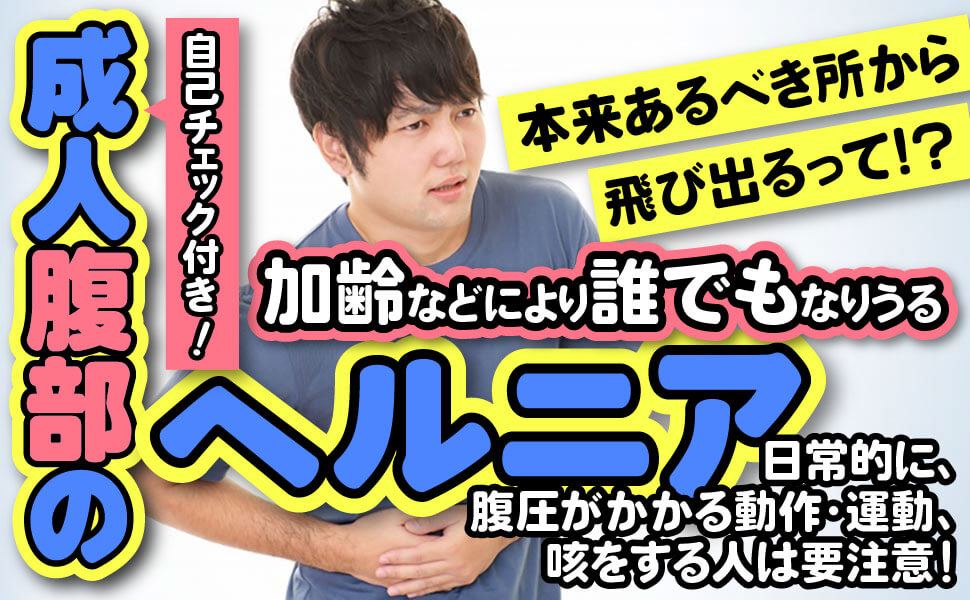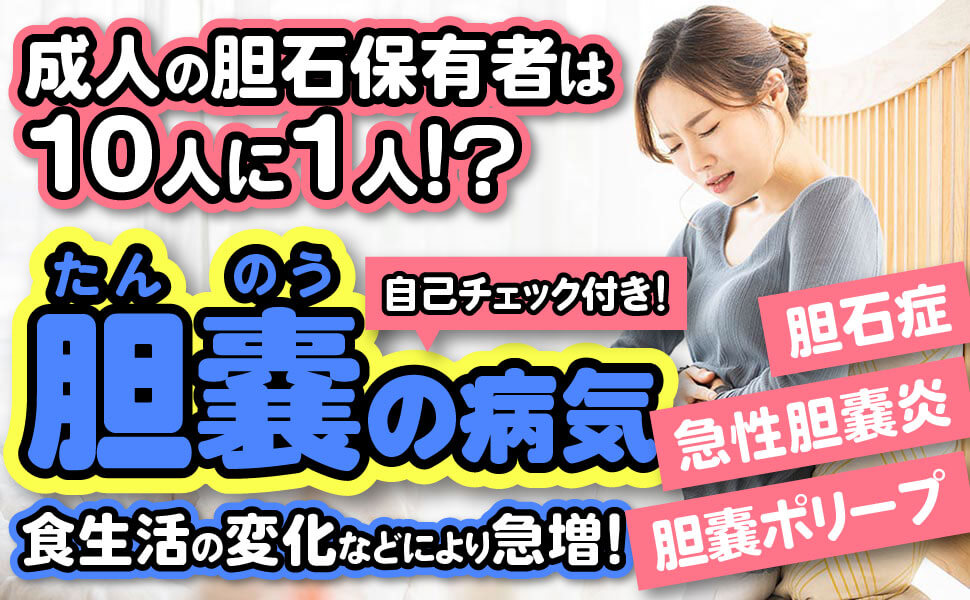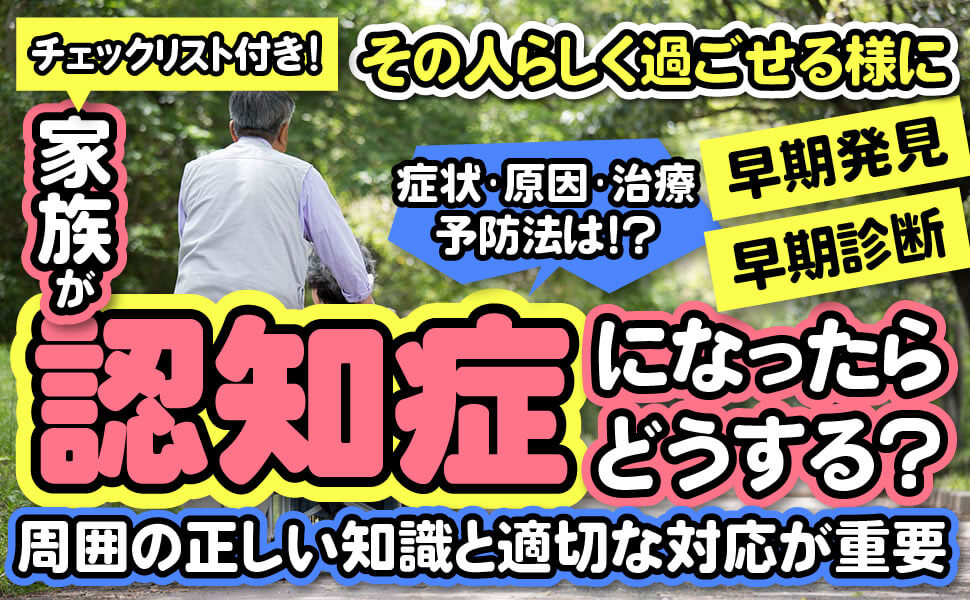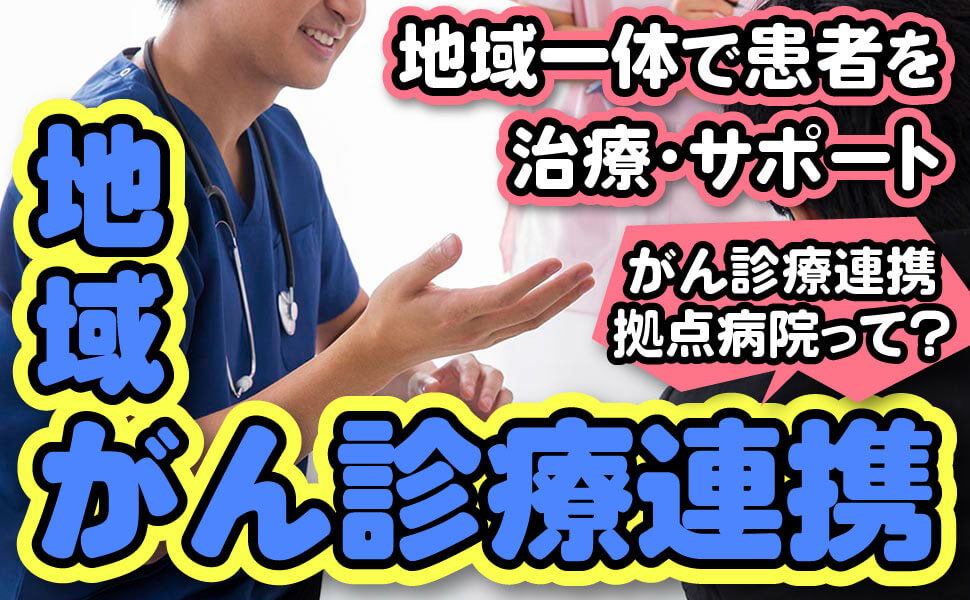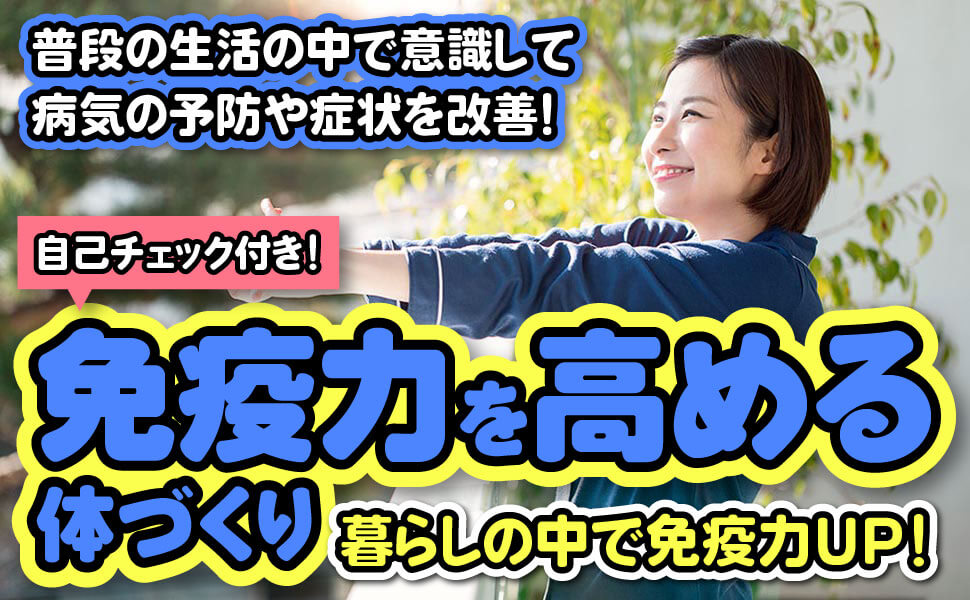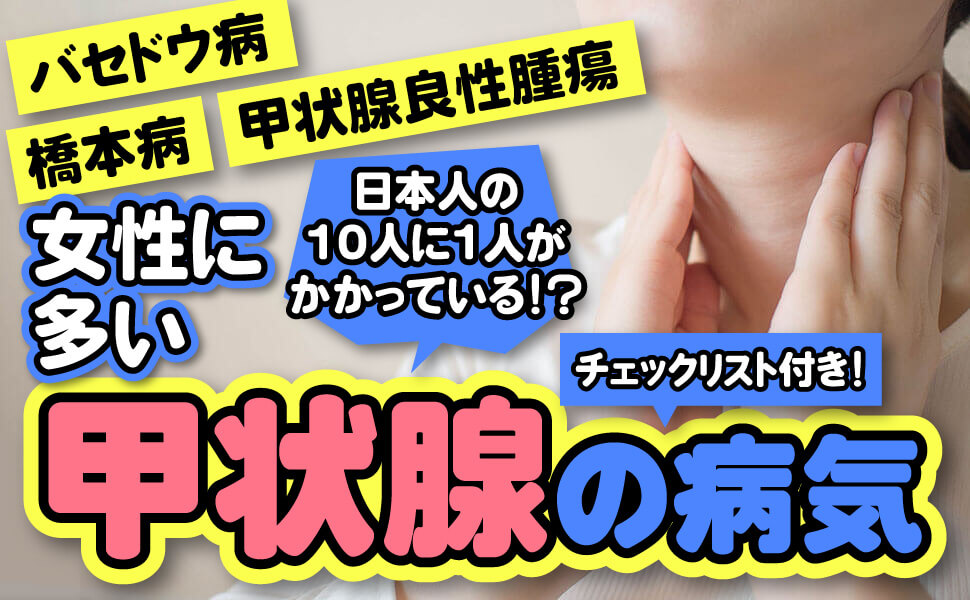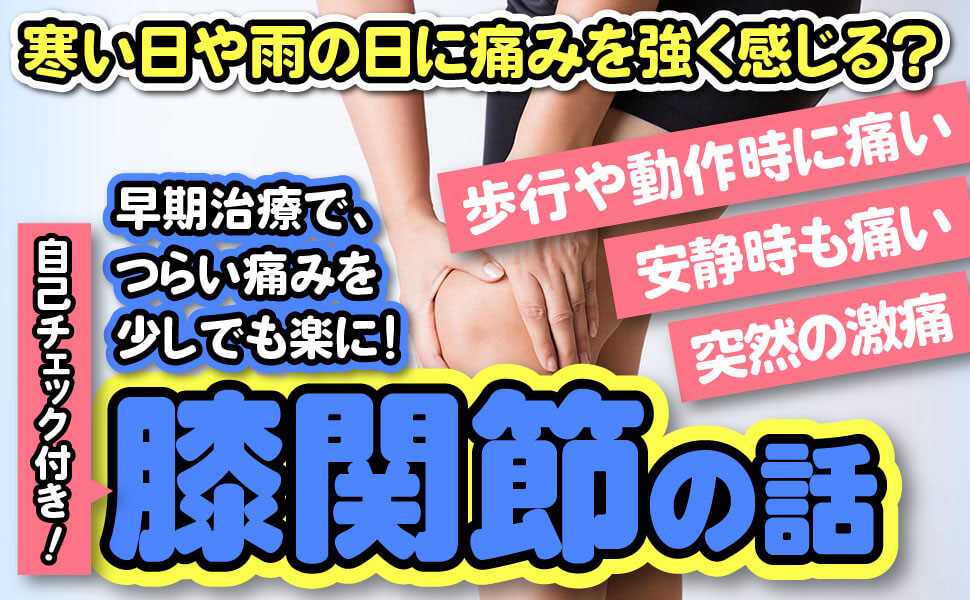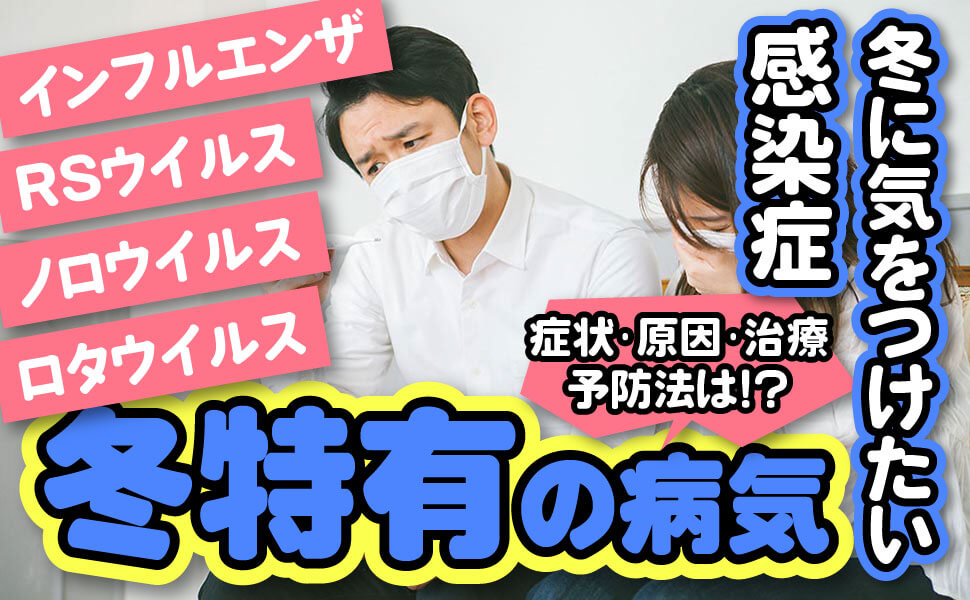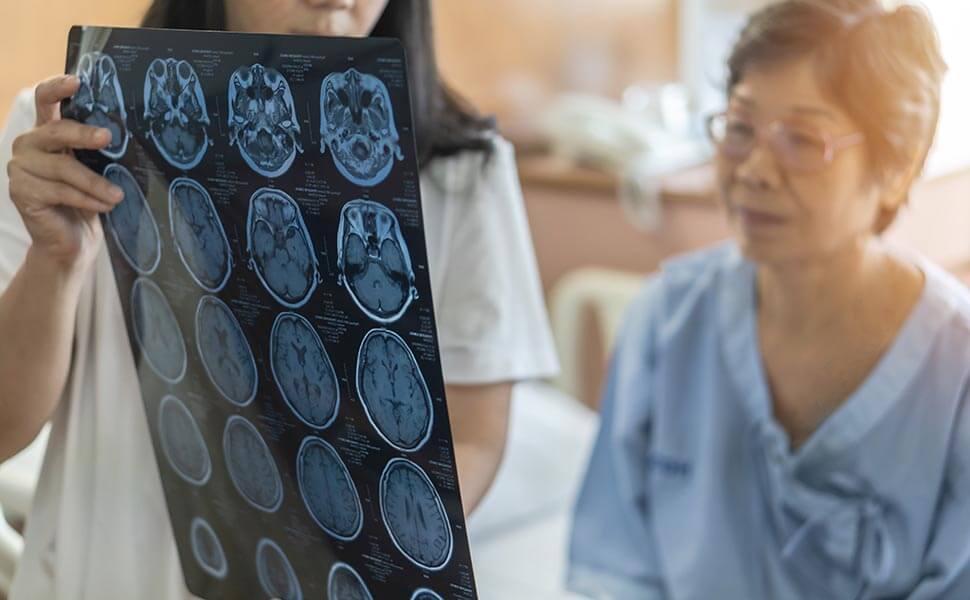Medical T. 編集部– Author –
-

加齢などにより誰でもなりうる病気
成人の腹部の ヘルニアヘルニア には様々な種類があり、発生部位によっては「脱腸」「でべそ」などの俗名も。ぽっこりと出ても、押し戻すと収まったりするため、放置しがちですが、悪化する前に受診し、現状を把握することが大切です。治療方法は手術のみ。専門病院では日帰り手術が可能。内蔵の病気 -

成人の腹部のヘルニア
鼠径ヘルニア -そけいヘルニア-鼠径ヘルニアとは、立っている時に足のつけね(鼠径部)がポッコリと膨らむヘルニア。外ヘルニアの8割~9割を占めています。中でも最も多い「外鼠径ヘルニア」は、体の右側で多く見られ、内鼠径輪を通って腹壁の外側に出現します。内蔵の病気 -

成人の腹部のヘルニア
臍ヘルニア -さいヘルニア-臍ヘルニア の「臍(さい)」は臍(へそ)の緒(臍帯)が閉じた跡であり、元々弱いため、肥満や妊娠による膨隆、腹水(お腹に水がたまる病気)などの持続的な腹圧の上昇に伴って発生しやすくなります。内蔵の病気 -

成人の腹部のヘルニア
大腿ヘルニア -だいたいヘルニア-大腿ヘルニア は鼠径鼠径部の下の脚に繋がる太もも部分(大腿)に小さな膨らみができます。大腿輪と呼ばれる脚につながる血管や神経が通る穴を塞いでしまうため、最も嵌頓(かんとん)しやすく、注意が必要です。疼痛を伴い、中年以降の痩せた女性(特に経産婦)に多く見られます。内蔵の病気 -

成人の腹部のヘルニア
腹壁瘢痕ヘルニア -ふくへきはんこんヘルニア-腹壁瘢痕ヘルニア とは開腹手術や外傷後の傷跡(瘢痕)が大きく膨らむ状態を指します。立った時、咳やくしゃみ、排便時などの腹圧がかかった時に発生することが多いヘルニアです。腹部の手術の合併症のひとつで、術後10年間で約1割の人に発症するといわれています。内蔵の病気 -

食生活の変化などによって急増!
胆嚢 の病気-たんのう-異常が生じても、初期では、ほとんど無症状であることが多いといわれる 胆嚢 。胆嚢に結石やポリープができていても自覚症状が無く、健診で偶然わかることも。 進行して症状が突然現れるため、日頃から規則正しい生活を心掛けるとともに、定期的に検診を受けることをお勧めします。内蔵の病気 -

家族が認知症になったらどうする?
認知症正しい理解と対応を知り、恐れずに向き合おう。 家族の誰かがいつなってもおかしくない「 認知症 」。偏った情報から、認知症に対して絶望的なイメージを抱く方も少なくありません。しかし、正しい対応と適切な治療によって改善するケースもあります。まずは、認知症を理解することから始めましょう。神経変性疾患 -

地域一体で患者を治療・サポート
地域 がん診療連携日本全国どこにいても、質の高いがん医療を提供できるよう設置されているのが「 がん診療連携 拠点病院」です。その仕組みや支援内容を理解し、がん治療に対する不安を和らげましょう。治療のことや仕事、お金の不安など何でも構いません。がんと診断されたら、まずは一度ご相談ください。未分類 -

普段の生活の中で意識して病気の予防や症状を改善!
免疫力 を高める体づくり元気で健康に過ごすために、 免疫力 は不可欠です。免疫力は病原菌から身を守り、健康を維持し、身体を若々しく保つ力があると言われています。免疫力が低くなると、病気だけでなく新陳代謝も低下して、さまざまな肌トラブルがおこることもあります。予防と遺伝 -

日本人の10人に1人がかかっている!?
甲状腺の病気甲状腺は、「元気の源」である甲状腺ホルモンを産生する大切な臓器です。正常に機能していないと、さまざまな症状が出現します。症状から他の病気と間違われる場合もあるため、専門医のいる病院を受診しましょう。内蔵の病気 -

早めの診察と最適な治療で症状をコントロール
小児アレルギー体の免疫システムが、食物や花粉、ダニ、汗など危険でないものにまで反応してしまう病気がアレルギーです。小児の場合はとくに、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、ぜん息などが代表的。アレルギーにかかった場合は、適切な治療を行い、症状をコントロールしていくことが大切です。アレルギー -

早期治療で、つらい痛みを少しでも楽に!
膝関節 のはなし膝関節 の痛みは軽度のうちに、適切な対処で進行を遅らせましょう。関節の中でも最も痛みを感じることが多いのが膝。関節のきしむ音や違和感が続いたら、関節の病気の予兆、早期発見への警鐘と考え、早めに専門医に相談しましょう早めの対処が、今後のQOL向上へのカギとなります。部位別の病気 -

冬特有の病気
冬に気をつけたい 感染症冬場はインフルエンザやノロウイルスなど色々な 感染症 が流行りやすく、高齢者の方は肺炎などにも気をつけなければならない季節です。 昔から言われていることですが、手洗いうがいは感染症の予防になりますので、特に冬場は徹底しましょう。ウイルス感染 -

乳幼児に多い感染性胃腸炎。ワクチン接種で重症化を防止
ロタウイルス 感染症ロタウイルス 感染症は6ヶ月~3歳の乳幼児に多く、48時間~72時間の潜伏期間についで嘔吐、下痢、発熱などの症状があらわれます。激しい嘔吐や下痢により脱水を起こしやすく、けいれん、肝炎などの合併症も認められます。生後6週から接種できるワクチンがあるので、ぜひ受けるようにしましょう。ウイルス感染 -

感染力が強いため感染者が出た場合は対策を入念に
ノロウイルス 感染症ノロウイルス 感染症は手指や食品などを介して経口で感染し、人の腸管で増殖するウイルス。24~48時間の潜伏期間のあと、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などの症状を引き起こします。ワクチン、特効薬がなく、感染した場合は点滴などでの対症療法となります。感染力が非常に高いため、感染を防ぐ工夫が必要です。ウイルス感染 -

乳幼児の感染に注意。重症化すると呼吸困難になることも
RSウイルス 感染症RSウイルス 感染症 は感染力が強いウイルスですが、ワクチンがありません。乳幼児の感染が多く、2歳までの間にほとんどの乳幼児が発症すると言われています。重症化すると気管支炎や肺炎などの症状を引き起こし、最重症の場合は呼吸器管理をしなければいけない場合もあります。ウイルス感染 -

流行前のワクチン接種で発病の可能性を低減
インフルエンザインフルエンザ の潜伏期間は平均3日(1~5日)。突然の発熱や筋肉痛、関節痛などの全身症状とともにのどの痛みや咳、鼻水などの気道症状があらわれます。流行前にインフルエンザワクチンを接種することにより、発病や重症化のリスクを軽減できることが分かっています。ウイルス感染 -

不妊の原因が明確な場合は早期治療を!
妊娠と 不妊 治療近年、約10組に1組が 不妊 のカップルと言われていますが、結婚年齢が高くなっている近年では、もっと高くなっていると想定できます。将来の自分やパートナーのためにも、妊娠に関する正しい知識を身につけておくことが大切です。不妊症・不妊治療 -

日頃からの生活習慣で予防を心掛けて!
脳の病気 脳卒中脳卒中 は、脳の血管が破れたり詰まったりして、脳の神経細胞が傷ついてしまう病気の総称です。脳梗塞(脳の血管が詰まる)、脳出血(血管が破れる)、くも膜下出血(動脈瘤が破れる)と、原因によって大きく3つに分類されます。脳・神経の病気 -

急な頭痛や吐き気は警告サイン!
くも膜下出血くも膜下出血 は、脳の血管にできた動脈瘤(どうみゃくりゅう)という瘤(こぶ)のように膨らんだ部分が破裂して、脳の表面に出血が広がる病気です。脳卒中の中では、最も死亡率の高い病気になります。出血が起こると、頭痛と吐き気を感じるので、感じた時は要注意です!すぐ病院を受診しましょう。脳・神経の病気 -

高血圧の人は要注意!
脳出血脳出血 は、脳内の細い動脈が血管の中の圧力に耐えられなくなり、破れることで起こります。出血は、脳を破壊しながら大きくなっていくため、後遺症が残ります。出血の場所によって、手足の麻痺、言語障害、ふらつきなど、後遺症はさまざまです。基本的に脳出血の原因は高血圧なので、血圧に注意することが大切です。脳・神経の病気 -

FASTが肝心!夏に多発!
脳梗塞 -のうこうそく-脳梗塞 は、脳の血管が詰まって血液が流れなくなるために、脳細胞が死んでしまう病気です。脳梗塞には、血栓(血のかたまり)が脳の血管の中にできて血管が詰まる脳血栓症と、心臓や血管の中にできた血栓が脳の動脈に流れ込んで血管を塞ぐ脳塞栓症があります。脳・神経の病気 -

日本人の2人に1人が発症する現代病の一つ
アレルギー の病気花粉症やアトピー性皮膚炎などアレルギーの病気に悩んでいる日本人は多く、今や日本人の2人に1人がアレルギー疾患を発症しているというデータもあります。 アレルギーが起こるメカニズムや、どんな症状が出るのかなど、アレルギーの病気について詳しく知っておきましょう。アレルギー -

繰り返す咳に注意。大人のぜん息も増加傾向に!
気管支喘息 (成人)気管支喘息 は気道にできた炎症によって、気道が狭くなり、そのために繰り返しの咳や、ゼーゼーヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)など、呼吸困難が生じる病気です。治療をせずに放置すると、気道内が変形し、さらに悪化する恐れがあります。早めに医師に相談しましょう。アレルギー -

花粉症の代表的な症状
アレルギー性鼻炎花粉症の代表的な症状である アレルギー性鼻炎 は花粉やダニ、ホコリなどが主なアレルゲンで、特に3月~4月にかけて患者が増える病気です。透明や白色をした水性の鼻汁がダラダラと出る、くしゃみや鼻詰まりを繰り返します。飲み薬や点鼻薬でアレルギー反応を抑える治療や免疫療法を行う場合もあります。アレルギー -

子どもに多い肌の病気
アトピー性皮膚炎アトピー性皮膚炎 は肌のバリア機能が不十分な人に発症する皮膚の病気で、かゆい湿疹が皮膚に繰り返し起こります。とにかくスキンケアをしっかり行うことが大切。紫外線を浴びすぎない、汗をかいたらこまめにシャワーを浴びるなどして、肌への刺激を最小限に抑えましょう。アトピー -

食後すぐに症状が出ることがほとんど
食物アレルギー食物アレルギー は人によりアレルゲンとなる食物が異なるため、検査を行います。アレルギーの場合は食後すぐに、じんましんや腹痛、嘔吐、咳などの症状が表れます。食物アレルギーは症状の出方や重症度に個人差があります。適切なアレルゲン診断を受け、医学的根拠に基づいた治療を行うことが大切です。アレルギー
1